さて、エゾメバルをひとしきり釣って満足したところでソイ釣りを再開。
スポーニング期のソイは、大型ほど沖の方から接岸してくるため、一般的には足元よりも沖に向かってキャストし少しでも「水深の深い場所にある地形変化」を探っていった方が、より効率がいい。特にクロソイ、マゾイ、シマゾイの大型はベッコウゾイやムラソイよりも元々好む水深が深いため、その傾向が顕著に出る。
案の定、しばらくしても反応がないため、沖の魚が釣れないのであれば、足元の敷石の隙間に潜んでいる居付きの中小型でもいいから釣っておこうかと、接近戦で足元付近を丁寧に探ったところ、少々スリムな体型ながら40UPのクロソイがヒットした。
ヒットルアーはガルプSWパルスワーム4”のホワイトグローの3/4ozテキサスリグで、ロッドはシューティンウェイSWC-802EXHスキップランを使っているので軽快にブチ抜く。

ただし、バイトは非常に小さく弱々しい感じで岩礁カウンターロック3/0の鋭利な針先がショートバイトを逃さず、絡め獲るようにホールドしてくれたおかげでフックアップに至った。
 ようやく魚の居場所のヒントを得たものの、その魚達の活性は著しいものではなかった。そこで、視点を変えてみることにした。それまではベイトタックルを使って沖の根まで遠投していたが、より繊細に丁寧に探りたいと思いスピニングタックルにチェンジ。
ようやく魚の居場所のヒントを得たものの、その魚達の活性は著しいものではなかった。そこで、視点を変えてみることにした。それまではベイトタックルを使って沖の根まで遠投していたが、より繊細に丁寧に探りたいと思いスピニングタックルにチェンジ。
スイミントレーサー(SWS-702L)の出番だ。ワームは喰い渋り時こそ頼りになるガルプSWダブルウェーブ3”にシフト。ダブルウェーブはタフになればなるほどその威力を発揮するマイクロベイトパターンにも対応する弱波動系ビジブル型ワレカラワーム。パルスワームより繊細かつスローに誘えるため、ここ一番!という時には、ぜひとも投入したい。リグは3/8ozライトテキサスにし、ストロークは長く取りつつもシェイキングを混ぜたリフト&シェイクフォールで攻める。シンカーが軽いこともあり、遠投しても底取りに必要以上に時間がかかってしまうため、足元から10m以内の区間に狙いを絞り、海底のわずかな段差やケーソンの隙間狙いに徹する。と、「コッ」という小さなバイトをしっかりと拾うと、フッキングと同時にロッドが大きく曲がる。更にドラグが「ジィ~~」と鳴り響く。
これはデカい!! 大興奮のやり取りの後に浮上したのは……。
でっぷりと太った50.5cmのクロソイ!! 重量も2.5kg強はあるだろう。
重量も2.5kg強はあるだろう。
この魚を待ってたのだ。ようやく報われた瞬間だ。



隣で釣りをしていた安瀬君。「あぁ~。パルスからダブルウェーブに変えたんですね。しまった…。ダブルウェーブのホワイトグローは今、切らしてしまっていたんですよね…。すいません、一つもらえませんか?」とのことで1パック渡すと、すぐにリグり直してキャスト。
すると…「来ました~。まぁまぁデカいですよ」との声。ベイトリールを新調したとのことで、まずは1尾ベイトタックルで釣りたいと気合を入れていたが、安瀬君が操るシューティンウェイSWC-722EXHブラインドサイトがいい具合に曲がっている。

浮上したのは、50cmのクロソイ。こちらもいいサイズだ!
この魚はホワイトグローのダブルウェーブを丸呑みで喰ってきていた。
これで二人とも50cm超えを達成し、十分満足出来る釣果を得た。
狙いの位置が正確に分かった。明らかに“釣れる通し方”が存在している。
そして問題なのは、単純に魚のステイジングルートを直撃するのではなく、いかにして「喰わせを誘う通し方」が出来るかどうかだ。
今日の場合は、もう時期、仔魚を放つための場所を探しに来ているクロソイの大型(親魚)は、コンブが揺らめく堤防の足元付近に沿って回遊してきていたのだ。確かに…不用意に沖に浮いてサスペンドしていたら、ソイの親魚自身もトドの餌食になってしまうかもしれないし、遠投すればその先の水深は18mに及ぶ。風も強い当日は過剰に早い潮流を避けつつ、これからの時期、放出していく仔魚を隠す場所(コンブのジャングルの中)を探して回遊して来た状態だったのだ。
又、それまで全く口を使わなかった魚達も周囲が真っ暗になったことで多少なりとも警戒心が緩んだのか、ようやく口を使い出してきた。
釣るなら今がチャンス。むしろ“今”、この時しかない。これが「時合い」というものだ。
タックル、釣り方、誘い方。“今”このタイミングでの釣り方を確信したことで、それからのラスト1時間はもっと凄かった……。
次回に続く。
タックルデータ
■ベイトタックル
●ロッド:シューティンウェイSWC-802EXHスキップラン
●リール:レボエリートIBHS
●ライン:シーガーR18フロロハンター16lb
●シンカー:カルティバ ブラスシンカー3/4oz
●クッションビーズ:オーナー夜光ビーズソフト原色4号
●フック:岩礁カウンターロック3/0
●ルアー:ガルプSWパルスワーム4”
■スピニングタックル
●ロッド:シューティンウェイSWS-702Lスイミントレーサー
●リール:ステラ3000HG
●ライン:シーガーテンヤ1号
●リーダー:シーガーショックリーダープレミアムマックス20lb
●シンカー:タングステンバレットシンカー3/8oz
●クッションビーズ:オーナー夜光ビーズソフト原色4号
●フック:岩礁カウンターロック3/0
●ルアー:ガルプSWダブルウェーブ3”
●偏光グラス:ZEAL OPTICS アルマジロ13
●偏光レンズ:TALEXモアイブラウン(夜釣り用)
★北海道留萌沖堤 渡船<留萌港>
■正宝丸 (斉藤船長 )【受付番号090-8633-8910】
2012年6月28日 |
カテゴリー:釣行記
 北海道の空の玄関口・新千歳空港。
北海道の空の玄関口・新千歳空港。
5月中旬、今回の北海道滞在では新千歳空港到着後、苫小牧市の勇払マリーナを拠点に、ロックフィッシュ、サケ・マス(トキシラズ、サクラマス)、各種カレイ、スルメイカなど狙う、今や道央圏において人気急上昇中の遊漁船、琉駕(読み=リュウガ。旧船名:ボイジャー)船長の安瀬君と合流し、留萌市にオカッパリでクロソイを狙いに行ったことから旅が始まった。
今回の旅ではロケの前後に、多少なりとも取材とは関係なしに純粋に釣りに向き合う時間も確保した(けっこう無理しましたが)。こういった釣行の積み重ねが商品開発のキッカケとなり、そして新しいテクニックの開発に繋がるので、場合によっては取材よりも得られることが大きい貴重な時間でもある。これまで私が手掛けた商品もこういった釣行の多くから発想が生まれており、プライベート釣行は年々減る一方ではあるものの、“初心忘れるべからず”の精神は今も大切にしている。
 今日は新千歳空港より北に位置する日本海側の留萌市に走る。
今日は新千歳空港より北に位置する日本海側の留萌市に走る。
途中で通った石狩川は雪代の影響でかなりの泥濁りになっていた。
北海道は雪の量が本州とは比べものにならないし、季節の進行が本州よりも遅いため雪代の影響は東北以上に気をつけておかないと、ドチャ濁りで川も海も釣りにならない時がある。このようなタイミングでは少しでも雪代の影響が少ない場所を絞り込んで行くのが得策である。
道中、高速道路脇にも残雪が残り、視界に入る山々にもまだ雪が見える。木々を見れば、まだ桜も咲いている。そう、季節はまだ春の始まりなのだ。
昼を回る頃からポツポツと雨が降ってきて、気温もいちだんと低くなった。今日はこれから風も強まり雨は本降りになる予報に、ちょっとガッカリしたが、予め決められた日程で動いているため、釣りそのものを中止しなければならない危険な荒天時以外は、最初から与えられた状況で割り切って釣りをすることにしている。天気の良い日だけを選んで釣りをしている時間は残念ながら取れない。
それに我々人間側の都合に、いちいち天気も魚も合わせてはくれない。釣れるか、釣れないかは釣り場に行って初めて分かるもの。要はモチベーションの持ち方次第。
現地に到着早々、上はヒートテック2枚重ねにその上にフリースを1枚、更にその上にレインスーツを羽織る。
下は雨に濡れてもいいように、更には防寒対策の意味も兼ねてウェーダーを着用する。
 15時。今ではすっかりメジャーになった留萌沖堤に正宝丸の齊藤船長に渡していただく。開口一番「やぁ佐藤さん、久しぶりだね~。待ってたよ。去年は…大変だったね。」と温かいお言葉を拝受した。
15時。今ではすっかりメジャーになった留萌沖堤に正宝丸の齊藤船長に渡していただく。開口一番「やぁ佐藤さん、久しぶりだね~。待ってたよ。去年は…大変だったね。」と温かいお言葉を拝受した。
ありがとうございます。ちなみに斉藤船長は元は静岡県の方。若い頃、勤め先の長期の出向仕事でこの留萌に来た時に、この海の豊かさに魅了され静岡県に戻らず、この地で渡船業・遊漁船業を開業したお方だ。
 北海道では主要な港町各地に沖堤があり、中でも函館、室蘭、石狩、留萌の沖防波堤に渡っての堤防オカッパリ釣りはロックフィッシュアングラーの定番になっている。堤防は磯とは違い、足場がいいので安全かつ快適に釣りが楽しめるところもうれしい。 さて―。自身2年ぶりに訪れた留萌沖堤。私達より先に6名の熱心なルアーアングラーが渡っていたが、釣況を訪ねるとバイトはまるでなく苦戦している、とのことだった。
北海道では主要な港町各地に沖堤があり、中でも函館、室蘭、石狩、留萌の沖防波堤に渡っての堤防オカッパリ釣りはロックフィッシュアングラーの定番になっている。堤防は磯とは違い、足場がいいので安全かつ快適に釣りが楽しめるところもうれしい。 さて―。自身2年ぶりに訪れた留萌沖堤。私達より先に6名の熱心なルアーアングラーが渡っていたが、釣況を訪ねるとバイトはまるでなく苦戦している、とのことだった。
というのも、周囲にはトドが接岸してきており、上物~底物に至るまで魚達は「トドを警戒して喰いが非常に悪い状況だよ。トドがいなくなるまでは、かなり難しいと思うよ。」と正宝丸の齊藤船長が言っていた。
本州ご在住の方にはなかなか実感が湧かないかもしれないが、北海道ではトドやアザラシ、シャチ、イルカといった海の大型哺乳類が岸近くまで接岸することがある。こういった海獣が岸近くまで寄ってきてしまうと、彼らのエサとなってしまう可能性のある魚達(つまり私達が釣っているような魚達)にとっては脅威にさらされている中、釣り人が投じたルアーやエサ釣り仕掛けなどには容易には口を使わなくなる。外敵から身を守るため、物陰にじっと隠れて警戒してしまうのだろう。こういう事例は本州ではあまりないため今一つ実感が湧かない方もいるかもしれないが、北海道の海ではこれまでオーシャントラウト~ロックフィッシュゲームに至るまで私はつくづく“この状態”を経験してきた。
 堤防に渡り、15時30分過ぎから釣りをスタートしたものの、ソイのバイトは20時までは一度もない厳しい状態が続き、誰もが皆、ボウズを覚悟していた。
堤防に渡り、15時30分過ぎから釣りをスタートしたものの、ソイのバイトは20時までは一度もない厳しい状態が続き、誰もが皆、ボウズを覚悟していた。
船長の言う通り、状況はかなり厳しいようだ。
唯一の釣果はアイナメ1尾だけ。ヒットルアーはガルプSWダブルウェーブ3”(カラー:ナチュラル)の3/4ozテキサスリグ。
にヒットしたアイナメ。留萌はアイナメの数が少ないので貴重です.jpg) 私などは何を釣っても楽しい性分ゆえ、ソイが釣れないならエゾメバル(ガヤ)狙いに徹し、一人でエゾメバル釣りを楽しんでいた。幸いにもエゾメバルだけは防波堤の際沿いのコンブジャングルの中に隠れているため、トドのプレッシャーも少ないのか、夕方になると同時に釣り人を楽しませてくれた。
私などは何を釣っても楽しい性分ゆえ、ソイが釣れないならエゾメバル(ガヤ)狙いに徹し、一人でエゾメバル釣りを楽しんでいた。幸いにもエゾメバルだけは防波堤の際沿いのコンブジャングルの中に隠れているため、トドのプレッシャーも少ないのか、夕方になると同時に釣り人を楽しませてくれた。
 宮城県以南在住の方だとエゾメバルを見たことない方もいると思うが、この魚は本州でお馴染みのメバルの仲間。冷水性のメバルということになる。アイナメよりも冷たい海を好むウサギアイナメがいるように、メバルよりも冷たい海を好むのがこのエゾメバルだ。道内では正式名称であるエゾメバルと表現する方は少なく、一般的には「ガヤ」の愛称で広く知られている。
宮城県以南在住の方だとエゾメバルを見たことない方もいると思うが、この魚は本州でお馴染みのメバルの仲間。冷水性のメバルということになる。アイナメよりも冷たい海を好むウサギアイナメがいるように、メバルよりも冷たい海を好むのがこのエゾメバルだ。道内では正式名称であるエゾメバルと表現する方は少なく、一般的には「ガヤ」の愛称で広く知られている。
 エゾメバルは青森や岩手でも時々釣れることもあるが、完全なる寒流域に生息するメバルなため、黒潮の勢力が残る宮城県沿岸までのエリアではこの魚にお目にかかることはない。ちなみに釣魚としては通常のメバルよりも皮が厚く筋肉質なため、エゾメバルの方が引きも強い。なので、あまりにもベナンベナンなULロッドなどではそれ相応のサイズを掛けるとすぐにコンブの中に潜られてしまい、獲り損ねる場合もあるから注意が必要だ。そして気性もメバルより荒く、アグレッシブな性質を持っているためルアーへの反応は抜群にいい。
エゾメバルは青森や岩手でも時々釣れることもあるが、完全なる寒流域に生息するメバルなため、黒潮の勢力が残る宮城県沿岸までのエリアではこの魚にお目にかかることはない。ちなみに釣魚としては通常のメバルよりも皮が厚く筋肉質なため、エゾメバルの方が引きも強い。なので、あまりにもベナンベナンなULロッドなどではそれ相応のサイズを掛けるとすぐにコンブの中に潜られてしまい、獲り損ねる場合もあるから注意が必要だ。そして気性もメバルより荒く、アグレッシブな性質を持っているためルアーへの反応は抜群にいい。
道内ではエゾメバルよりも大きな根魚が沢山いるためか、メバリングは正直なところ人気がない。
 しかし、小物とは言えこれだけルアーに反応良い魚を、みすみす釣らないのも勿体ないので、ぜひ本腰を入れて狙ってみてほしいと思う。本州のメバル釣りが人気の高まりとともに「数釣り」と「型狙い」の両方向に分かれていったように、エゾメバルも二通りの楽しみ方が可能な魚だ。
しかし、小物とは言えこれだけルアーに反応良い魚を、みすみす釣らないのも勿体ないので、ぜひ本腰を入れて狙ってみてほしいと思う。本州のメバル釣りが人気の高まりとともに「数釣り」と「型狙い」の両方向に分かれていったように、エゾメバルも二通りの楽しみ方が可能な魚だ。
現に石川県の能登島水族館の水槽ではかつて40cm強のエゾメバルが堂々と水槽の中で泳いでいるのを見て、「やっぱりエゾメバルも最大は40cmになるのだな~」と深々と悟ったことがある。又、茨城県に住む学生時代の友人の話では、同県の大洗水族館の水槽にも「40cmほどのエゾメバルが泳いでいたよ」と聞いた。ということは40cmが存在する以上、エゾメバルの“尺”(30cm)は現実的なサイズであり、狙って獲れるゲームフィッシングとして間違いなく確立出来る釣りである。
肝心なのは、やり方次第だと思う。
あれは2005年8月のことだったが、当時の私は釧路~知床半島までを雑誌の取材で釣り歩いた時、知床半島の漁港の夜釣りでコンブ際から30cmの尺ガヤを釣った時は凄くうれしかった思い出がある。それを見たカメラマンも我慢の限界に達したようで自分の車から申し訳なさそうにタックルをちょいと出してきて31cmの尺ガヤを釣って仕事そっちのけで喜んでいた(笑)。それ以来、私はこの魚の魅力に完璧にハマってしまったわけだ。30UP=尺オーバーのエゾメバルだけを専門的に狙う釣りを道内でやっている人は現時点、それほど多くはないはずなので人よりも先に“尺ガヤ”を獲るための釣り場と釣り方を見いだせれば、きっと面白い釣りが出来るはずである。
それでいて、やはりメバル族であるがゆえにルアーには著しくスレてくるから、同じ場所で同じ釣りばかりやっていると次第に見切られて釣れなくなってくる。それは同時に高いゲーム性をも意味し、このテクニカルさが釣りとしての深みを醸し出してくれるので、私は道内の夜釣りに行く際は必ずライトロックタックルを1本用意している。
当日のエゾメバルの釣果はご覧の通り。コンディションも抜群。
シューティンウェイSWS-702Lスイミントレーサーはラインポンドを落とせば、実はメバル用2g~3gジグヘッドをも普通に飛ばせるライトアクションロッド。フロロのみならずPEラインにも対応するKガイド仕様なので、良型のメバルやエゾメバル(ガヤ)、ソイなどを釣っていてスルメイカ(マイカ)やヤリイカが回遊してきたときにはワームから小型のエギに結び変えてそのままエギング出来るブランクのシャープさと力強さも持ち合わせているため年間を通して出番は多い。
元々、大型根魚狙いでのフィネスアプローチ用として開発した細見軽量でありながら、平均にして50cm/2kgの大型根魚が掛かった時に最大限に楽しめる作りに設定している肉厚ブランクのトルクは3キロオーバー、4キロオーバーの巨大根魚が掛かっても真向から勝負出来る点も見逃せない。手のひらサイズのライトロック~4キロ級のヘビーロックまで使える、1本あるととても便利なスピニングロッドだ。

これだけ釣れると本当に楽しい。
それでも安瀬君や周囲のルアーアングラーは終始、ソイ狙いに徹していたが、私は一人たんたんと久々のエゾメバルゲームを十分に満喫していた。
しかし、その時点ではこの後にとんでもない事が起きるとはまだ知らずに……。
次回に続く。
タックルデータ
■スピニングタックル<エゾメバル用ライトロックタックル>
●ロッド:シューティンウェイSWS-702Lスイミントレーサー
●リール:ステラ2000
●ライン:シーガーR18ライトPE0.4号
●リーダー:シーガーショックリーダープレミアムマックス5lb
●ジグヘッド:クロスヘッド2g~3g
●ルアー:ガルプSWベビーサーディン2”、ガルプSWサンドワーム2”
●偏光グラス:ZEAL OPTICS Vanq、アルマジロ13
●偏光レンズ:TALEXイーズグリーン
TALEXモアイブラウン(夜釣り用)
※原則としてサングラス及び偏光グラスの夜間着用は視野が暗くなるため視界確保が難しく危険防止の観点から好ましくありませんが(事実、夜間運転時のサングラス着用は厳禁です)、夜間でもわずらわしい光を安全にシャットアウト出来、夜間でも着用できる偏光グラスとしてTALEX初のJIS規格を得ているのがモアイレンズ(モアイブラウン及びモアイグレー)です。私は夜釣りの際は、モアイブラウン着用しています。このレンズを着用することで夜においても安全に必要な明るさを確保しながら浅瀬の根やウィード、潮目が浮き上がって見えるコントラスト性能を発揮してくれるのでメバルやエゾメバル、クロソイ、アジ、シーバス、ナマズなどのナイトゲームもされる釣り人の皆さんにはオススメの偏光レンズです。
詳しくは下記(↓)TALEX光学工業のウェブサイトにてご確認下さい。
http://www.talex.co.jp/product/lenscolor.html
★北海道留萌沖堤 渡船<留萌港>
■正宝丸 (斉藤船長 )【受付番号090-8633-8910】
2012年6月27日 |
カテゴリー:釣行記
★プロズワンからのお知らせ★
大手自動車メーカー・本田技研工業株式会社(ホンダ)の「Honda釣り倶楽部」ウェブサイトに、佐藤文紀が実釣をおこなった北海道積丹半島アイナメ記事が掲載されました。
■北海道/積丹半島のアイナメ
積丹ブルーに輝くロックフィッシュ天国
http://www.honda.co.jp/fishing/column/column-20120620/index.html
ぜひ、ご一読下さいませ。
2012年6月26日 |
カテゴリー:雑誌掲載・DVD
しばらく続いた長期ロケを終えたのはいいものの、地元・宮城県に帰って来てからも連日の忙しさのあまりご報告が遅くなってしまったが、去る5月20日(日)は北海道札幌市のプロショップ・ノースキャスト様主催「佐藤文紀実釣セミナー&アングラーズパーティー」が室蘭市を会場に開催された。

当日は、札幌圏を始め開催地・室蘭近郊などからも多数の方々にお集まり頂き、誠にありがとうございました。

例年、取材や開発テストで道内の各地のフィールドを訪れても、熱心なロックフィッシュアングラーの皆さんとこうして共にロッドを振る機会は少ないゆえ、今回はこの素晴らしい時間を同志の皆様方と共有出来ましたこと自身、大変うれしく思っております。

中にはお父さんと一緒に参加してくれた小学生の男の子や高校生、女性アングラーの姿もあり、各々のスタイルで誰もが気軽にエントリー出来るロックフィッシュゲームの人気と親しみやすさを改めて実感致しました。
今回のイベントは主催頂きましたプロショップ・ノースキャスト様は勿論のこと、会場の確保に多大なる尽力頂きました室蘭市様の全面的なご協力、そして沖堤への渡船でお世話になりましたスターマリンK.K.「つりぶねや」様、ご当地の“今”を取材する新聞社の「室蘭民報社」様をはじめとする沢山のご協力を賜りましたことで、イベントが事故や怪我もなくスムーズに進行出来またこと重ねて厚く御礼申し上げます。
又、ご協賛頂いたピュア・フィッシング・ジャパン様、クレハ合繊(シーガー)様、グレンフィールド(ZEAL OPTICS)様、つり人社北海道支社様にも大変感謝しております。





 当日は室蘭港に5つある沖堤のうちの一つ、絵鞆(えとも)沖堤を貸し切りという形でイベントを開催させて頂きました。「あれ…なんか、この防波堤って来たことあるような…?」と思ったら、どうりで昨年11月発売の「ロックフィッシュ地獄7」のロケ地となった所。ここでは風速10mを超える強風が吹き荒れるスーパータフコンディションの中、シューティンウェイSWS-702LスイミントレーサーにガルプSWダブルウェーブ3”(カラー:ナチュラル)の3/8ozジグヘッドリグを使い、マーキングPE0.8号による「テンション0⇔100釣法」を駆使して54cmのオスのアイナメを獲った思い出の地。
当日は室蘭港に5つある沖堤のうちの一つ、絵鞆(えとも)沖堤を貸し切りという形でイベントを開催させて頂きました。「あれ…なんか、この防波堤って来たことあるような…?」と思ったら、どうりで昨年11月発売の「ロックフィッシュ地獄7」のロケ地となった所。ここでは風速10mを超える強風が吹き荒れるスーパータフコンディションの中、シューティンウェイSWS-702LスイミントレーサーにガルプSWダブルウェーブ3”(カラー:ナチュラル)の3/8ozジグヘッドリグを使い、マーキングPE0.8号による「テンション0⇔100釣法」を駆使して54cmのオスのアイナメを獲った思い出の地。
偶然とはいえ、7ヶ月振りに戻ってきた同場所に懐かしさとうれしさが込み上げてきました。
当日は、朝イチこそ渋かったものの午前9時を回る頃には参加者の皆さん大物のヒットが相次ぎ、55cm、53cm、51cmといった大物アイナメに、46cmのカジカ、黄色いボディーに黒いストライプが非常に美しいシマゾイも4、5本も揚がり、和気あいあいとした雰囲気に。
沖に遠投すると砂地という地形柄、主に足元のケーソンの隙間や穴の中などのスリットを丹念に攻めていたアングラーにバイトが集中したようだった。シンカーは決して重すぎない範囲のウェイトをセレクトし、いずれも丁寧に繊細に攻めることで、より多くのバイトを捉えていた。
当日の詳細は主催店様のイベント報告(↓)を併せてご参照下さい。
http://ameblo.jp/north-cast/entry-11256450596.html
又、実釣後にはアングラーズパーティーを開催。
北海道名物のジンギスカン、カニ汁、ホタテ飯などが、なんと食べ放題。

肉も美味いし、アイナメ同様カニが大好物の私は、おかわりして(笑)カニ汁を堪能しました。
好天にも恵まれ、美味しい食事をバーベキュー形式で味わえ、多くのアングラーの皆さん方と、とても楽しく有意義に過ごせた至福のひとときでした。
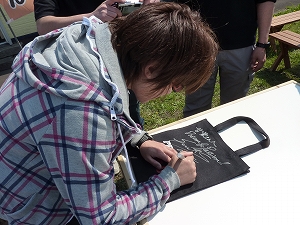
北海道室蘭市は苫小牧市と並んでアイナメの魚影がすこぶる濃い一級の地。それだけに港湾部の人的プレッシャーも相当なものだが、それでも尚、これだけの魚達が棲める環境が維持されているのには道内にしっかり根づいているキャッチ&リリースの精神によるところが大きい。

考えれば、トラウトの聖地でもある北海道は、イトウにしてもアメマスにしても釣った魚を大切に扱い、きちんとリリースする習慣がビギナー層まで意識的に浸透しているところは大変素晴らしいことだと思う。トラウトルアーに関しても海サクラを除いては、シングルフックの使用がごく当たり前になったのも、うなずける。
それだけにロックフィッシュに関しても、不必要な魚や小さい魚は持ち帰ることなくキープは最小限に慎み、元気なうちに積極的にリリースしてきたからこそ、今日の根魚釣りが成り立っている。
これからもロックフィッシュゲームが末永く楽しめる環境が残していけるよう、こういった高い意識の持ち方・心ある活動をぜひとも引き継いでいってほしい。

イベントにご参加頂きました皆さん、誠にありがとうございました。
ぜひ、またの機会にお会い致しましょう。
追伸:このイベントの様子は5月25日(金)の室蘭民報(株式会社 室蘭民報社)に詳細が掲載されました。
新聞の掲載記事はこちら(↓)をご参照下さいませ。
http://ameblo.jp/north-cast/image-11262647129-11997688531.html
2012年6月25日 |
カテゴリー:雑誌掲載・DVD
現在発売されている6月8日(金)リリースのノースアングラーズ2012年7月号(つり人社)では留萌市の沖堤オカッパリロックフィッシュゲームを披露している。
 北海道の地名はアイヌ語に漢字を当てたものが大半なため、本州在住の方で、北海道を訪れたことのない方には普段なかなか聞き慣れない地名も多いかと思う。事実、「留萌(るもい)」という場所についても、留萌(るもえ)と読み方を誤認しているケースもあるので、その辺はぜひ注意深く気をつけてみたい。私自身、留萌市を訪れたのは2年振りで、その時は「ロックフィッシュ地獄6」の取材とシューティンウェイ各機種のプロトタイプを持ちこんでのテストをおこなった思い出深い土地の一つである。
北海道の地名はアイヌ語に漢字を当てたものが大半なため、本州在住の方で、北海道を訪れたことのない方には普段なかなか聞き慣れない地名も多いかと思う。事実、「留萌(るもい)」という場所についても、留萌(るもえ)と読み方を誤認しているケースもあるので、その辺はぜひ注意深く気をつけてみたい。私自身、留萌市を訪れたのは2年振りで、その時は「ロックフィッシュ地獄6」の取材とシューティンウェイ各機種のプロトタイプを持ちこんでのテストをおこなった思い出深い土地の一つである。
2年前。当時、開発途中だったシューティンウェイSWC-802EXH“スキップラン”でプリスポーンの40UPシマゾイを釣り上げたのもこの留萌で、昔からデカいシマゾイをひたすら釣りたくて、「せたな町」から北上しつつ釣り歩き、ようやく辿り着いたこの地で、狙いに狙っていた憧れの魚が闇夜の水面に浮上した際にはハンパなく興奮したのを、まるで昨日のことのように思い出す。
釧路を中心に十勝~根室など道東方面に局地的に多く生息するウサギアイナメと、どちらかというとサイズを狙うなら日本海側が有利となるシマゾイは私にとって日本国内に生息する根魚における最高ランクに位置づけているレアなロックフィッシュ。希少価値で言えばキジハタやベッコウゾイより遥かに上をいっている魚達だ。ちなみにシマゾイは稀に岩手や宮城の沖釣りで釣り上げられるケースもあるが、基本的に寒流色が強い魚種であるため両魚種に関しては通常、本州ではお目にかかれない。だからこそ、北海道に釣りに行く価値がある。どうしても釣りたい魚がいるならば、その魚がいる場所まで自分の意志で赴く。憧れの魚を必死に追いかけ“自分の手に抱く”醍醐味は心を激しく揺さぶる。まさにロマン溢れる、夢の釣り旅なのだ。
 さて、話を戻すと本来であれば、今回の取材は積丹半島でのアイナメ取材を予定していたのだが、取材日があいにくの強風によるシケ模様の天候で危険と判断し、取材が延期となってしまった。
さて、話を戻すと本来であれば、今回の取材は積丹半島でのアイナメ取材を予定していたのだが、取材日があいにくの強風によるシケ模様の天候で危険と判断し、取材が延期となってしまった。
積丹半島のアイナメ釣りと言えば舞台が磯が主になるだけにシケの荒波では岩場には立てないから、これでは仕方ない。が、この後にはショップさん主催の実釣セミナー、TVロケ、DVDロケが相次いで迫っていたため時間的猶予はない。元々、私の訪道スケジュールに合わせて企画して頂いている取材だけに入稿〆切まで残り数日、更にはカメラマンさんの都合も今日か明日しかスケジュール確保出来ない状況で、私的にも取材を行なえる時間も予め決められているため「とりあえず、安全に取材出来る場所ならどこでも結構ですよ」と思っていたら、留萌の方が早く風が収まっていく予報とのことで、それならと留萌でのクロソイ狙いに変更して取材を決行した。
 まだ残雪が残る中、桜の花が咲いている5月中旬。北国もようやく釣りのハイシーズンに突入し、出版社側もカメラマンも私もそれぞれのスケジュールが満杯なため取材日を仕切り直すことは無理だったため場所を変えて強行した。
まだ残雪が残る中、桜の花が咲いている5月中旬。北国もようやく釣りのハイシーズンに突入し、出版社側もカメラマンも私もそれぞれのスケジュールが満杯なため取材日を仕切り直すことは無理だったため場所を変えて強行した。
でもこれが大正解。世の中って不思議なものですね。
思えば、ロックフィッシュの取材においては過去最高の釣果をマーク。何と言っても“大物の数釣り”を心底堪能出来たから凄い。
先日のブログでもお伝えしているように北海道の日本海側は太平洋側に比べアイナメそのものの生息密度がそう多くはない上にサイズにしても太平洋側ほど大きくならないで成長が止まる魚がほとんど。その分、太くなる。
特に道内では北に行けば行くほどその傾向が顕著で、道北圏に近づけば近づくほど大型のアイナメは期待出来ない。その代り、アイナメに代わって勢力を拡大するのが北方系フサカサゴ属のソイとエゾメバルである。ソイはクロソイが主で時々マゾイ(キツネメバル)とシマゾイ、ムラソイ&オウゴンムラソイ(北海道の地方名で言うハチガラ)が加わる。
そういう観点から見てもソイのルーツは北国にあり、クロソイの本場は北海道であることは容易に想像につく。
 ただし、北海道には生息しないベッコウゾイや関東以南にまで勢力を拡大していったムラソイ族だけは、やや温かい水温を好むことからその勢力を本州でより拡大していった種族に違いない。
ただし、北海道には生息しないベッコウゾイや関東以南にまで勢力を拡大していったムラソイ族だけは、やや温かい水温を好むことからその勢力を本州でより拡大していった種族に違いない。
さて―。留萌に到着すると港で私達を出迎えてくれたのは、いつもお世話になっている正宝丸の齊藤船長。早速、堤防に渡して頂く。沖堤とはいえ、基本的にはあくまでも防波堤なので私の中では、そこが沖に突き出した場所にあるのか、それとも地続きの防波堤なのかの違いくらいでしかないが、私の地元である三陸では連なる磯場が防波堤の役目をしている独特の地形柄、旧来から沖堤自体が少ない海ゆえ、「わざわざ沖堤に乗って防波堤釣りをする」という概念が定着せず、結果的には沖堤での釣り文化は一般的に広く浸透しなかった経緯がある。
なので、三陸エリアでロックフィッシュを楽しんでいるアングラーには沖堤への渡船と言うとなんとなく敷居が高いように感じてしまう方もいらっしゃるかもしれないが、北海道では堤防でのオカッパリをするのに沖堤への渡船はごく普通のこと。それほどメジャーなんです。平日でも仕事帰りのお父さん方が、夕方から沖堤に渡ってちょいと夜釣りするのに17時過ぎ、18時過ぎから乗ってくるほどだ。
 よって、人気のある沖堤ともなれば夕方になるとエサ釣り~ルアー釣りに至るまで多くの釣り人でワイワイ、ガヤガヤと賑わいを見せる。
よって、人気のある沖堤ともなれば夕方になるとエサ釣り~ルアー釣りに至るまで多くの釣り人でワイワイ、ガヤガヤと賑わいを見せる。
この日は宿泊拠点になっていた余市のホテルまでカメラマンが迎えに来て下さり、それからスタッフ全員で留萌に向かった。ホテルを出たのは夜10時半過ぎだったので留萌に到着したのは午前1時半過ぎ。そこから仮眠して早朝に沖堤に渡船して頂き、夜明けからのデイゲームでクロソイを狙った。
結果は誌面をご覧の通り。
なんと開始2投目からいきなりプリスポーンの45cmオーバー・2kg後半のクロソイがホワイトグローカラーのガルプSWダブルウェーブ3”の3/8ozライトテキサスにヒット。続く3投目には同ルアーで50cmのクロソイがヒットし、一気に眠気がぶっ飛ぶ!!
その後は最大55cm(3.2kg)の極太ランカーを筆頭に50UPのクロソイが8本、45UPが30本、45cm未満は多数につきカウントせず…という驚愕の釣果を叩き出すことに成功した。
タックルは9割方スピニングタックル・シューティンウェイSWS-702Lスイミントレーサーによるもので、ベイトタックルではなくあえてスピニングタックルでラインスラッグを生かして軽やかにフワフワ誘いを掛けたことが圧倒的なバイトを引き出すことに繋がったと思う。
又、ベイトタックルを使うにしてもここではシューティンウェイSWC-802EXHスキップランにPEラインをセットした“PE版”の「ヘビーライト釣法」を駆使し、ヘビータックルながらライトテキサスを軽快に扱うことが可能な同ロッドでのフィネスアプローチこそが数々の大物クロソイのショートバイトを的確にモノに出来た結果となった。
産卵を控えたソイはアイナメ以上に水質や水温にもすごく神経質になるし、人が多いハイプレッシャーの釣り場では、よりライトリグが強みを増してくる。釣り場の状況・魚の活性に合わせて的確にタックルとリグを使いわけたいものだ。
クロソイの他にはアイナメ、ホッケ、エゾメバル(ガヤ)、カジカも混じり、最終的には五目釣り達成。
堤防からのオカッパリでこれだけの釣果が出せるって本当に凄いこと。
 ドラグの鳴り方でだいたいの大きさが判別つくが、これだけ50UPのクロソイを連発してしまうと感覚が完全にマヒしてしまい、入れ食いの最中には水面に浮上した45cm前後、重量にして2~2.5kgクラスのクロソイを小型だと錯覚してしまっていたから恐ろしい…。仕舞には45cm前後のソイならライトなスピニングタックルにも関わらず、気がつけば手っ取り早く豪快にブチ抜いてしまっていた……。
ドラグの鳴り方でだいたいの大きさが判別つくが、これだけ50UPのクロソイを連発してしまうと感覚が完全にマヒしてしまい、入れ食いの最中には水面に浮上した45cm前後、重量にして2~2.5kgクラスのクロソイを小型だと錯覚してしまっていたから恐ろしい…。仕舞には45cm前後のソイならライトなスピニングタックルにも関わらず、気がつけば手っ取り早く豪快にブチ抜いてしまっていた……。
取材中に釣ったソイのアベレージサイズは40cmオーバー。45cm~48cmでまぁまぁサイズ。50cmで「おっ、いいサイズ!」、53~55cmで「よっしゃー!」という、とんでもない爆釣劇だった。
こんな奇跡の大爆釣経験は今後二度と出来ないかもしれないが、その日のクロソイの活性にアジャストした釣りが展開出来たことが爆釣への扉を開く最大の要因になったと強く感じた。
大型のソイ=ヘビーベイトタックルと思われる方も多いことだろう。しかし、その中にあってより大物のヒットを連発したのは圧倒的にスピニングタックルによるライトテキサスによるものだった。ワームは3インチ。ガルプSWダブルウェーブ3”のホワイトグローカラーとブラックカラーがダントツで釣れた。続いて同ワームのCGBFO、ナチュラル、レッドの順で良く、カモ、モエビ、レッドバグキャンディーといった地味系や透過系カラーへの反応はお世辞にも良いものではなかった。ホワイトグローとブラックの2大カラーのソイへの反応の良さは釣っている本人もビックリするくらい、あからさまに偏ってバイトが集中した。(釣れ過ぎてこの2色だけ途中でワームのストックが無くなりましたが…。)
また、幾度となく投入したビッグワームは驚くことに、ことごとく撃沈。大型ソイへの実績が高い6インチのパルスワームも、今回に限っては8インチのガルプSWイールや10インチワーム共々まるでバイトなし。4インチのパルスワームでやっとアタリが出る感じ。当日の状況では明らかにワームサイズとワームカラーを巨ゾイ達は選り好みして喰ってきていたことになる。
 東北ロックフィッシュシーンでは現在もワームサイズは4インチが主流で、3インチだと小さいと思っているアングラーも少なくないだろう。確かに、振り返れば近年の東北は一般的に釣り方も釣法もずっと停滞したままになっている。要は釣り方を進化・発展させるよりもフィールドパワー(場所の力)で釣っていた感も正直否めない。
東北ロックフィッシュシーンでは現在もワームサイズは4インチが主流で、3インチだと小さいと思っているアングラーも少なくないだろう。確かに、振り返れば近年の東北は一般的に釣り方も釣法もずっと停滞したままになっている。要は釣り方を進化・発展させるよりもフィールドパワー(場所の力)で釣っていた感も正直否めない。
しかし、魚も賢く進化していくように釣る側の私達もそれ以上に釣技に磨きをかけ発展させなくてはならないのだ。
現にお隣の北海道ではワームサイズは3インチが主流で、タフコンディション下では2インチワームも積極的に用いて釣果を揚げている。しかも釣っている魚は東北よりも全般的にデカい魚が多いにも関わらず、だ。
これは使うワームが小さいからといって釣っている魚も小さいとは限らないことを意味し、ブレードテキサスを始めとするブレードリグの発展系である「スプーンリグ」やダウンショットリグの発展系である「アンカーリグ」、そして軽いリグをヘビータックルで扱う「ヘビーライト釣法」やスピニングタックルにマーキングPEラインを使った「テンション0⇔100釣法」を編み出したのも、現代における最先端のフィッシングシーンに合わせた進化系そのものなのだ。
.jpg) 本州同様、人的プレッシャーの高まりと共にタフコンディション化が進んでいる道内のフィールドにおいても、年を追うごとに繊細に誘わなければ口を使ってくれない魚も増えてきていることは私もよく痛感している。
本州同様、人的プレッシャーの高まりと共にタフコンディション化が進んでいる道内のフィールドにおいても、年を追うごとに繊細に誘わなければ口を使ってくれない魚も増えてきていることは私もよく痛感している。
そういう時代背景も伴って、人的プレッシャーの高いオカッパリゲームでは既に3インチワームが主流・定番化した北海道では、4インチのワームだけでは対応出来ないケースが出てきたというアングラー達の率直な声であり、何よりの証なのだろう。これが示しているものは何なのか、ということを今回は自身改めて実感させられた。
 その証拠に近年のシーバス界では小型バイブレーションによるマイクロベイトパターンの威力が注目を集めているし、スレたデカバス狙いのサイトフィッシングでは、ためらいもなく2インチワームを投入するバスアングラーも近年では多い。
その証拠に近年のシーバス界では小型バイブレーションによるマイクロベイトパターンの威力が注目を集めているし、スレたデカバス狙いのサイトフィッシングでは、ためらいもなく2インチワームを投入するバスアングラーも近年では多い。
東北ロックフィッシュゲームにおいても、3インチワーム=小物の数釣り用という、いつの間にか構築されていった誤解を解かなくてはならない時代に差し掛かっていることを、北のフィールドで今一度、再確認した有意義な釣行となった。
タックルデータ
■スピニングタックル<ライトテキサス>
●ロッド:シューティンウェイSWS-702Lスイミントレーサー
●リール:ステラ3000HG
●ライン:シーガーテンヤ1号
●リーダー:シーガーショックリーダープレミアムマックス20lb
●シンカー:タングステンバレットシンカー 3/8oz
●クッションビーズ:オーナー夜光ビーズソフト原色4号
●フック:岩礁カウンターロック3/0
●ルアー:ガルプSWダブルウェーブ3”
■ベイトタックル<ヘビーライト釣法PEバージョン&スプーンリグ>
●ロッド:シューティンウェイSWC-802EXHスキップラン
●リール:レボエリートIBHS
●ライン:シーガーバトルJライト1.5号
●リーダー:シーガーショックリーダープレミアムマックス20lb
●シンカー:タングステンバレットシンカー3/8oz、1/2oz
●クッションビーズ:オーナー夜光ビーズソフト原色4号
●フック:岩礁カウンターロック3/0、2/0
●ルアー:ガルプSWダブルウェーブ3”
※スプーンリグは20g前後で8cm前後の細みのスプーンが最適で、岩礁カウンターロック2/0とガルプSWダブルウェーブ3”をセットするのが基本。
●偏光グラス:ZEAL OPTICS Vanq、アルマジロ13
●偏光レンズ:TALEXアクションコパー、TALEXイーズグリーン
TALEXモアイブラウン
★北海道留萌沖堤 渡船およびボートロック・ガイド船<留萌港>
■正宝丸 (斉藤船長 )【受付番号090-8633-8910】
2012年6月24日 |
カテゴリー:雑誌掲載・DVD
« 前のページ
次のページ »

 ようやく魚の居場所のヒントを得たものの、その魚達の活性は著しいものではなかった。そこで、視点を変えてみることにした。それまではベイトタックルを使って沖の根まで遠投していたが、より繊細に丁寧に探りたいと思いスピニングタックルにチェンジ。
ようやく魚の居場所のヒントを得たものの、その魚達の活性は著しいものではなかった。そこで、視点を変えてみることにした。それまではベイトタックルを使って沖の根まで遠投していたが、より繊細に丁寧に探りたいと思いスピニングタックルにチェンジ。 重量も2.5kg強はあるだろう。
重量も2.5kg強はあるだろう。











 今日は新千歳空港より北に位置する日本海側の留萌市に走る。
今日は新千歳空港より北に位置する日本海側の留萌市に走る。 15時。今ではすっかりメジャーになった留萌沖堤に正宝丸の齊藤船長に渡していただく。開口一番「やぁ佐藤さん、久しぶりだね~。待ってたよ。去年は…大変だったね。」と温かいお言葉を拝受した。
15時。今ではすっかりメジャーになった留萌沖堤に正宝丸の齊藤船長に渡していただく。開口一番「やぁ佐藤さん、久しぶりだね~。待ってたよ。去年は…大変だったね。」と温かいお言葉を拝受した。

にヒットしたアイナメ。留萌はアイナメの数が少ないので貴重です.jpg)
 宮城県以南在住の方だとエゾメバルを見たことない方もいると思うが、この魚は本州でお馴染みのメバルの仲間。冷水性のメバルということになる。アイナメよりも冷たい海を好むウサギアイナメがいるように、メバルよりも冷たい海を好むのがこのエゾメバルだ。道内では正式名称であるエゾメバルと表現する方は少なく、一般的には「ガヤ」の愛称で広く知られている。
宮城県以南在住の方だとエゾメバルを見たことない方もいると思うが、この魚は本州でお馴染みのメバルの仲間。冷水性のメバルということになる。アイナメよりも冷たい海を好むウサギアイナメがいるように、メバルよりも冷たい海を好むのがこのエゾメバルだ。道内では正式名称であるエゾメバルと表現する方は少なく、一般的には「ガヤ」の愛称で広く知られている。 エゾメバルは青森や岩手でも時々釣れることもあるが、完全なる寒流域に生息するメバルなため、黒潮の勢力が残る宮城県沿岸までのエリアではこの魚にお目にかかることはない。ちなみに釣魚としては通常のメバルよりも皮が厚く筋肉質なため、エゾメバルの方が引きも強い。なので、あまりにもベナンベナンなULロッドなどではそれ相応のサイズを掛けるとすぐにコンブの中に潜られてしまい、獲り損ねる場合もあるから注意が必要だ。そして気性もメバルより荒く、アグレッシブな性質を持っているためルアーへの反応は抜群にいい。
エゾメバルは青森や岩手でも時々釣れることもあるが、完全なる寒流域に生息するメバルなため、黒潮の勢力が残る宮城県沿岸までのエリアではこの魚にお目にかかることはない。ちなみに釣魚としては通常のメバルよりも皮が厚く筋肉質なため、エゾメバルの方が引きも強い。なので、あまりにもベナンベナンなULロッドなどではそれ相応のサイズを掛けるとすぐにコンブの中に潜られてしまい、獲り損ねる場合もあるから注意が必要だ。そして気性もメバルより荒く、アグレッシブな性質を持っているためルアーへの反応は抜群にいい。











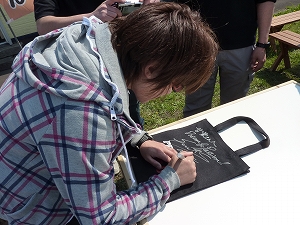



 さて、話を戻すと本来であれば、今回の取材は積丹半島でのアイナメ取材を予定していたのだが、取材日があいにくの強風によるシケ模様の天候で危険と判断し、取材が延期となってしまった。
さて、話を戻すと本来であれば、今回の取材は積丹半島でのアイナメ取材を予定していたのだが、取材日があいにくの強風によるシケ模様の天候で危険と判断し、取材が延期となってしまった。
 ただし、北海道には生息しないベッコウゾイや関東以南にまで勢力を拡大していったムラソイ族だけは、やや温かい水温を好むことからその勢力を本州でより拡大していった種族に違いない。
ただし、北海道には生息しないベッコウゾイや関東以南にまで勢力を拡大していったムラソイ族だけは、やや温かい水温を好むことからその勢力を本州でより拡大していった種族に違いない。 よって、人気のある沖堤ともなれば夕方になるとエサ釣り~ルアー釣りに至るまで多くの釣り人でワイワイ、ガヤガヤと賑わいを見せる。
よって、人気のある沖堤ともなれば夕方になるとエサ釣り~ルアー釣りに至るまで多くの釣り人でワイワイ、ガヤガヤと賑わいを見せる。

 東北ロックフィッシュシーンでは現在もワームサイズは4インチが主流で、3インチだと小さいと思っているアングラーも少なくないだろう。確かに、振り返れば近年の東北は一般的に釣り方も釣法もずっと停滞したままになっている。要は釣り方を進化・発展させるよりもフィールドパワー(場所の力)で釣っていた感も正直否めない。
東北ロックフィッシュシーンでは現在もワームサイズは4インチが主流で、3インチだと小さいと思っているアングラーも少なくないだろう。確かに、振り返れば近年の東北は一般的に釣り方も釣法もずっと停滞したままになっている。要は釣り方を進化・発展させるよりもフィールドパワー(場所の力)で釣っていた感も正直否めない。.jpg)
 その証拠に近年のシーバス界では小型バイブレーションによるマイクロベイトパターンの威力が注目を集めているし、スレたデカバス狙いのサイトフィッシングでは、ためらいもなく2インチワームを投入するバスアングラーも近年では多い。
その証拠に近年のシーバス界では小型バイブレーションによるマイクロベイトパターンの威力が注目を集めているし、スレたデカバス狙いのサイトフィッシングでは、ためらいもなく2インチワームを投入するバスアングラーも近年では多い。